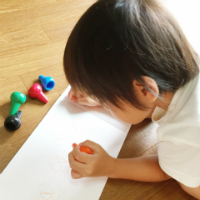
お子様の成長サポートに
糖鎖が発達障害の改善に効果を発揮するのではないかという意見が挙げられるようになりました。そこで今回は、糖鎖と発達障害にはどのような関係があるのか考えていきたいと思います。
さとう所長、糖鎖は小さい子供の成長をサポートするって本当ですか?
そうですね。明確に効果があるとわかっているというわけではありませんが、発達障害のお子さんに糖鎖栄養素を摂らせてみたところ、嬉しい変化があったという方もいるようです。
糖鎖は本当に万能なんですね!
まずは、発達障害とはどんなものか一緒に見ていきましょう。
- 1 そもそも発達障害とは
- 1.1 主な発達障害の種類と特徴
- 1.2 ダウン症と発達障害の違い
- 2 原因について
- 3 発達障害と糖鎖の関係
- 3.1 糖鎖は脳神経の形成にも深く関わっている
- 3.2 糖鎖栄養素の体験談
- 3.3 ただし糖鎖栄養素で発達障害が治ることは証明されていない
- 4 糖鎖異常が引き起こす体の不調
- 5 糖鎖を整えるためには?
- 6 まとめ
そもそも発達障害とは
ひと口に「発達障害」といっても、いくつかの種類に分けられます。まずはその種類ごとにどんな特徴があるのかを見てみましょう。
主な発達障害の種類と特徴
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 自閉症 | 他人との関係を築くのが苦手、言葉の発達が遅い、興味や関心のある特定のものにこだわるなど。先天性の疾患であるといわれており、3歳までに何らかの症状が見られる場合が多い。 |
| アスペルガー症候群 | 言葉の発達や知的発達の遅れはないものの、他人とコミュニケーションをとったり、相手の気持ちを察することが難しい。原因の多くは家庭や遺伝によるものといわれているが、はっきりとはわかっていない。 |
| LD(学習障害) | 知的発達に大きな遅れはないものの、書く・聞く・話す・計算するといった特定の能力が困難。本格的な学習をはじめる小学生頃まで、判断することが難しい。 |
| ADHD(注意欠陥/多動性障害) | 集中力がない、落ち着きがない、順番が待てないなどの特徴がある。小さい子供であればだれにでも表れる要素なので、障害として認識されづらい。 |
ダウン症と発達障害の違い
ダウン症は、約1000人に1人割合であらわれる先天性の症候群のこと。通常23組46本の染色体のうち、21番目の染色体が1本増えることが原因で起こります。
ダウン症も広義の意味では発達障害に当てはまりますが、自閉症やアスペルガー諸侯群などと違い、原因は卵子や精子の分裂異常、もしくは受精時に起こる染色体異常であることがはっきりとわかっています。
大部分の発達障害は乳児出生前に形成されるが、一部は出生後の外傷、感染症、その他の要素に起因することもある[2]。原因は多々あるが、たとえば以下が挙げられる[12]。 遺伝子や染色体の異常 - ダウン症候群、レット症候群など
引用元:発達障害 - Wikipedia
原因について
発達障害の原因は、医学的に解明されていません。しかし現在考えられる原因として、主に遺伝的要因と環境的要因に分けられています。
遺伝的な要因
発達障害の原因は、遺伝的要因の可能性が考えられるといわれています。例えば、一卵性双生児の場合、2人ともに発達障害があらわれる割合は75~85%ほどだといわれています
しかし単純に「親が発達障害であれば、子にも同じように発達障害が起こる」というわけではありません。現在発達障害の遺伝についてはさまざまな研究がされていますが、その確率についてはまだ明らかになっていない状態です。
環境的な要因
原因の1つとして、環境汚染も関係しているのではないかといわれています。これは、ダイオキシンや重金属、水銀などが脳に悪影響を与えているのではないかというもの。これらの物質を取り除くことで改善が期待できるのではないかという説もあるようです。
また子供の偏食についても問題視されています。必要な栄養が摂れていない、また特定の栄養のみを過剰に摂ってしまっていることが、発達障害の原因となっているのではないかという説です。
しかしこれらの説は、どれも根拠と呼べるものがなく、現在も研究されている段階です。
不妊治療で生まれた子供さんの方が発達障害の割合が多いようです。母体の栄養状態が悪いと、低出生体重児や神経、精神の発達の遅れが起こりやすくなります。出生後に十分な栄養補充ができれば取り戻すことができますがそのような子供さんは腸が悪いことが多く食物アレルギー、小食、偏食であったりしてなかなか難しいようです。
引用元:不妊治療で生まれた子供さんに発達障害が多い!: Dr.靖子のblog
発達障害は先天的な脳の機能障害で、遺伝などの原因によって発症するという見解が多数ですが、毎日摂っている食事や栄養にも原因があるのではないかという意見も増えています。
毎日の食生活による栄養の過不足やアレルギーが、脳や神経の働きを不安定にし、腸内環境を悪化させていると言う意見もあります。
引用元:発達障害の原因と栄養と食事 | 発達障害の子供とお母さんが幸せに生きる方法
発達障害と糖鎖の関係
糖鎖は、8つの糖の組み合わせでできる、細胞のアンテナです。免疫細胞のコントロールや、細胞の質の管理など、体のさまざまな機能は、糖鎖によって細胞同士が情報交換をすることで正しく働いています。
この糖鎖、基本的には食べ物から合成されるのですが、偏食が続くと体内で十分な量が合成されなくなってしまいます。
発達障害の原因にはさまざまなものがありますが、「偏食によって糖鎖がうまく作られない」ことが、その症状に拍車を掛けているのではないか、という考えも。
発達障害が完治することはありませんが、症状を改善するためには栄養療法が効果的とされています。その効果が、糖鎖が正常化されたことによってもたらされている可能性も十分あり得ます。
糖鎖は脳神経の形成にも深く関わっている
2017年10月、新潟大学の研究グループが、大脳の神経形成に少量のコンドロイチン硫酸(糖鎖の一種)が関係していることを世界で初めて発見してニュースになりました。
大人より子どもの方が学習能力が高い、というのは良く知られていますが、これは子どもの脳が成長期であることが理由です。今回明らかになったのは、子どもの脳の成長を促すのが、少量のコンドロイチン硫酸であるという点。
コンドロイチン硫酸は大人の大脳にも豊富に存在しており、その役割は神経回路形成の抑制でした。そのため、神経回路の形成にはコンドロイチン硫酸以外の何かが関与していると思われていたのですが、実際には同じ物質(コンドロイチン硫酸)の量で調整されていた、ということのようです。
糖鎖についてはまだわからないことが多く、研究が進められている状況です。しかし今後その働きが明らかになることで、発達障害を改善に導いてくれる可能性は十分にあると言えます。
近年、臨界期やPV細胞の機能異常が、精神疾患(自閉症、統合失調症など)の一因となることが示唆されています。さらに、精神疾患の誘因とPV細胞の周囲に蓄積するコンドロイチン硫酸との関連が報告されつつあるため、将来的には、コンドロイチン硫酸による PV 細胞の機能の改善が、精神疾患の症状の軽減に繋がることも期待されます。
引用元:《コンドロイチンが大脳の柔軟性を制御する》-脳内コンドロイチンによる神経回路の成長促進-/新潟大学
糖鎖栄養素の体験談
まだその根拠は明らかになっていませんが、実際に糖鎖栄養素を摂取して、お子様の様子が好転したという方もいらっしゃいます。
食べ始めて3ヶ月ぐらいから徐々に暴言がなくなり始め、勉強も落ち着いてできるようになり、成績が向上しました。
言葉に遅れのある3歳の息子に飲ませて3週間が経過しました。言葉の理解と表出が爆発的に進んで驚いています。
引用元:【楽天市場】購入者さんのたけしの家庭の医学で「糖鎖」が紹介されました![シーズ糖鎖]Seeds糖鎖免研CAM糖鎖栄養素販売元1箱【2g×30包】 | みんなのレビュー・口コミ
ただし糖鎖栄養素で発達障害が治ることは証明されていない
アメリカでは、糖鎖栄養素を含んだサプリメントによってダウン症の症状が改善した、という体験談をまとめた書籍(書名:A Gift Called Michelle)が出版されたりもしていますが、その著者の主張はメーカーによって否定されるなど、物議を醸しています。糖鎖栄養素を摂取することで発達障害が改善する、ということは断言できません。
ただ、糖鎖が脳の神経形成に関わっているというのは、ほぼ間違いのないことです。
また、糖鎖を摂る=栄養バランスの整った食事を摂る、ということでもあるため、たとえ糖鎖を摂ることに大きな効果がなかったとしても、健康上マイナスになることはありません。
糖鎖異常が引き起こす体の不調
発達障害とも関係があると考えられている糖鎖ですが、糖鎖が乱れることによって、そのほかに体にはどんな影響があるのでしょうか。
糖鎖には、私たちの体の健康を保つという役割があります。ひとつひとつの細胞に鎖のように繋がっている糖鎖は、いわば細胞の司令塔。
その細胞に異常が起きてしまうと、細胞同士はコミュニケーションを取ることができなくなり、必要な細胞を保護したり、ウイルスや細菌と戦うなどの本来の役割を果たすことができなくなってしまいます。
糖鎖は、発達障害以外にも、肝臓病や関節リウマチ、癌、アルツハイマー、インフルエンザ、さらには不妊症などと関係していることが明らかになっています。
糖鎖と病気の関係についてはまだ明らかになっていないことも多くありますが、糖鎖の異常が私たちの体の不調になんらかの影響を与えているということは、紛れもない事実です。
糖鎖を整えるためには?
糖鎖は、8種類の糖鎖栄養素と呼ばれる糖が鎖のように繋がってできています。糖鎖を整えるためには、この8種類の糖鎖栄養素を食事から摂取したり、肝臓での合成を促すという方法が考えられます。
8種類の糖鎖栄養素が、どんな食べ物に含まれているのか、詳しく見てみましょう。
| 糖鎖栄養素 | 含まれている食べ物 |
|---|---|
| グルコース | 炭水化物、果物、野菜 |
| ガラクトース | 牛乳やチーズなどの乳製品、ツバメの巣 |
| マンノース | アロエベラ、ツバメの巣、こんにゃく |
| フコース | メカブやもずくなどの海藻類、キノコ類、ツバメの巣 |
| キシロース | 穀物や植物の皮、メープルシロップ |
| N-アセチルグルコサミン | ツバメの巣、甲殻類 |
| N-アセチルガラクトサミン | ツバメの巣、牛乳 |
| N-アセチルノイラミン酸 | ツバメの巣、母乳 |
なかなか聞きなれない名前が並んでいますが、まずは、グルコースとガラクトースが含まれている食べ物に注目してみましょう。
グルコースは、「炭水化物、果物、野菜」、ガラクトースは「牛乳やチーズなどの乳製品、ツバメの巣」に多く含まれていることがわかります。
実は食事から十分な量を摂取できるのは、8種類の糖鎖栄養素のうち、この2種類だけ。残りの6種類の糖鎖栄養素は、食事からは十分な量を摂取することができません。
8種類の糖鎖栄養素を含む食材として挙げられるのが、高級食材として知られるツバメの巣。しかしツバメの巣を毎日食卓に並べることは難しいでしょう。
これらの糖鎖栄養素は、食事で摂取するほか、肝臓で合成することも可能です。しかし肝臓で合成するためには多大なエネルギーと時間が必要となるため、簡単なことではありません。
食事からの摂取、肝臓での合成という2つの方法では、どちらも体に必要な量を確保するのは難しいのです。
そこで有効なのが、健康食品から糖鎖栄養素を摂取するという方法です。8種類全ての糖鎖栄養素がバランス良く配合されている物を選べば、手軽に糖鎖を整えることができます。
まとめ
少し難しい話もありましたが、まとめると「糖鎖が発達障害に効果があるかははっきりとはわかっていない。でも実際に糖鎖栄養素を摂取したことで良い効果があった人もいる。」ということですね。
ざっくりまとめると、そんなところですね。障害にどう働くかはわかっていないとしても、糖鎖は体のさまざまな不調に関係しているものなので、整えて何か悪いことが起こるということはありません。